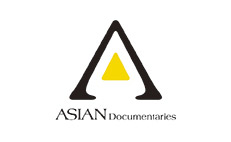東京ドキュメンタリー映画祭 > 上映作品 > 至極の美術工芸
上映作品
特別2至極の美術工芸
12月16日(木)12:10〜上映
千葉県千倉町においてうちわの制作過程を記録した映像を、兄が弟に見せる劇中劇に仕立てあげた伝説の民俗誌映画
『うちはの出来るまで』。沖縄県瀬底島で、唯一の作り手となった大城善雄の笠づくりと生活を記録した『むんじゅる笠』。美術工芸の名人芸に迫るだけでなく、真摯に向きあう職人の姿をイメージに焼きつけた至極の2編。
-


-
作品1
うちはの出来るまで 上映時間12分
うちわの制作過程を記録した映画を、兄が弟に見せるという劇中劇のような構成にしている。うちわ作りの行程は、千葉県千倉町のうちわ屋で撮影された。職人の全体の動きと、手元のアップをバランスよく撮影し、制作の過程を分かりやすく表現している。宮本馨太郎がカメラを手にして2年後の昭和5年、民俗誌映画の制作に没頭し始めた頃の作品。映画の中で映画を見せるという斬新な構成は、他の馨太郎作品では見られない。1930年/12分
監督のことば
宮本馨太郎は1937年(昭和12)、「パテーシネ協会」関東支部主催の映画作品協議会で「郷土映画」部門を設定。地方の自然、生活、文化、民俗、風土、行事などに関わる映画作品を全国から募集、コンテストを開いた。発展させようとしたその試みも、その後の日中戦争、太平洋戦争によって中断された。監督プロフィール

-
宮本馨太郎
1911−79年 旧制中学時代の1928年(昭和3)の16歳の時、仏製の9.5ミリカメラ、パテーベビーを購入して撮影を開始。初めての民俗記録映画「海女」を房州平館で撮る。立教大学在学中は映画同好会をつくり活動。17歳で父勢助に連れられアチック・ミューゼアムで渋沢敬三に会う。その後、渋沢の旅の多くに同道し、数多くの民俗誌映像を残した。『花祭をたづねて』(1930)、『八丈島の記録、島の生活』(1931)、『越後竹沢村角突』(1935)、『珍しい深田の田植え』(1936)、『パイワン族の再訪記録』(1937)ほか多数。
-


-
作品2
むんじゅる笠 瀬底島の笠 上映時間92分
むんじゅる笠とは麦わらと竹で作る日よけの笠。舞台は沖縄県本部町の西の海にある瀬底島。島の多くの人が副業としてむんじゅる笠を作り、笠の材料が足りないときは島外へ調達に出かけた。現在、瀬底島でたった一人となったむんじゅる笠の作り手が大城善雄さんである。この作品は、善雄さんの野良笠と踊り笠(琉球舞踊「むんじゅる」)の製作工程と瀬底島の神事、むんじゅる笠と共に生きた島の暮らしを描いた作品。2021年/92分
監督のことば
むんじゅる笠を知らない人に伝えたい、技術を残したいと思い製作を決意した。大城善雄さんとご家族、瀬底島の皆さんの全面的な協力で撮影することができたが、資金面でも初挑戦のクラウドファンディングで381名様のご支援で工面することができた。みんなでつくった映画という思いが強い。感謝しかない。この映画を通してどの地域にも課題となっている伝統文化継承について自然との共生について考えてもらいたいと思う。監督プロフィール

-
城間あさみ
幼稚園教諭勤務後映像製作の世界へ。製作会社に10年間勤務し20本の映像作品を演出。退職後、フリーランスとして活動。2006年元の製作会社の演出部の仲間と映像製作『海燕社』結成、本格的に映像製作活動再開。2010年『海燕社』を法人化し代表に就任。市町村祭祀を中心に20本以上製作。主な作品に『ふじ学徒隊』(2012年/脚本)。